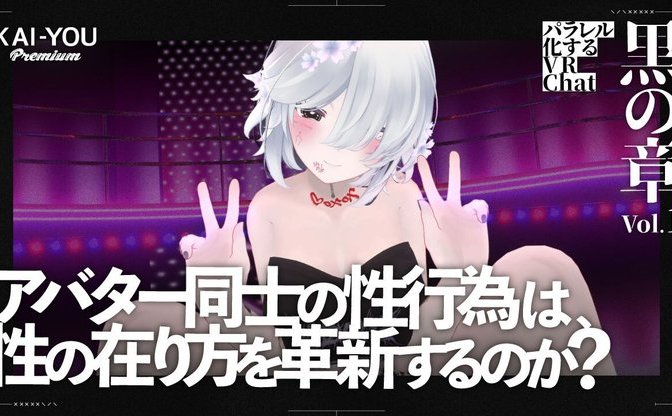
パラレル化するVRChat──黒の章──by xiutx
VRChatには、多層的な文化が広がっている──
ライター・xiutxによる「パラレル化するVRChat──黒の章──」では、失われつつあるVRChatのアンダーグラウンドな側面に光をあてる。VRChatが形成する独特なコミュニティに潜入し、レポートや分析を行っていく。

連載
一つのテーマを、連続した企画として発信していく「連載」は、KAI-YOU Premiumの目玉コンテンツの一つです。
単発では伝わりづらい長期的視野を見据えたテーマはもちろん、気になる識者や著名人のロングインタビューや、特定のテーマを掘り下げたレポートやレビューなどを発信していきます。
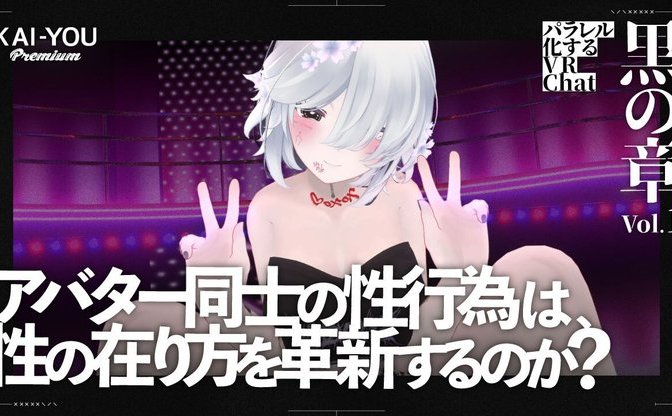
VRChatには、多層的な文化が広がっている──
ライター・xiutxによる「パラレル化するVRChat──黒の章──」では、失われつつあるVRChatのアンダーグラウンドな側面に光をあてる。VRChatが形成する独特なコミュニティに潜入し、レポートや分析を行っていく。

VRChatには、多層的な文化が広がっている── ライター・浅田カズラによる「パラレル化するVRChat──白の章──」では、さらなる発展と進歩を遂げていくVRChatの先進的な側面に光をあてる。VRChatの未来を占うコミュニティやクリエイターに取材し、レポートや分析を行っていく。

英語圏を中心に世界から人気を獲得しているVTuber・アイアンマウス。配信企画「サバソン(Subathon)」で集めた寄付金約7400万円を、VShojoが資金流用していた事件を受けて独立を発表。その後のチャリティーで120万ドル(約1億7000万円)を超える寄付金を集めた彼女に聞く、脱退の真相。

絶え間なく注目の的が移り変わり、故に風化も早く、実態が掴み難いVTuberシーン。これをメディアでもファンでもない、VTuber当人の視点でアーカイブ化。後世に歴史資料として残すことを目指す。
語り手は、鋭い洞察と豊かな経験を持つVTuber・九条林檎。美学に生きる彼女と共に、月に一回、話題になったトピックに切り込んでいく。
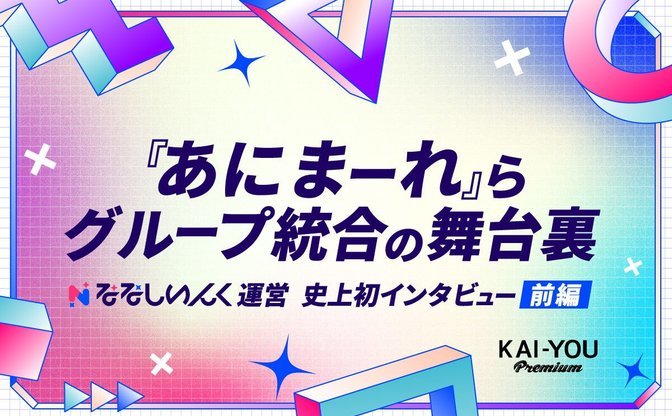
「『運営が表に出る』ことは避けてきた」
そう語るのは、VTuberブームの黎明期・2018年より「有閑喫茶あにまーれ」「ハニーストラップ」などのグループを世に送り、業界に独自の存在感を放ち続けている「ななしいんく」。2023年3月には、所属グループ全ての統合を行い、事務所名を「774inc.」から「ななしいんく」に改名したことも話題を呼んだ。
しかし、その運営体制やスタッフについてはほとんど全て謎に包まれていた。KAI-YOU Premiumでは、そんな「ななしいんく」の運営にメディア初インタビューを実施。前後編にて、創業期から大規模な組織変更に至るまでの道のりと、あまり語られない「事務所から見た視点」について話を聞いた。
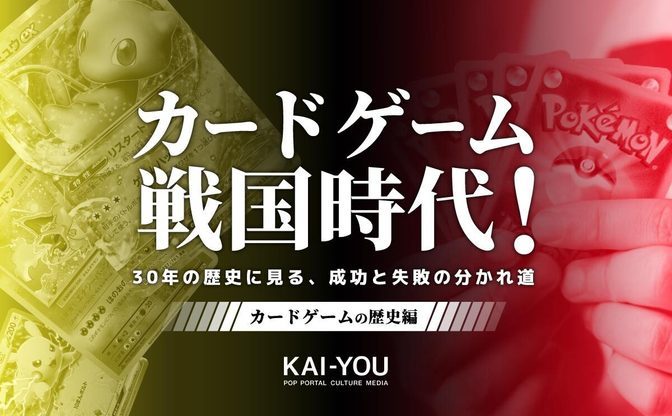
2023年度のカードゲーム・トレーディングカードゲーム(TCG)の国内売上は、希望小売価格ベースで2774億円(日本玩具協会調べ)であり、2020年度の1222億円から、わずか2年で倍増。TCG業界は現在、空前のバブル景気を迎えている。ゲームデザイナーとしてTCGの開発・運営に携わる一方で、古今東西のTCGを観察・分析してきたJey.P.氏による、TCGの歴史まとめ、およびトレンド分析と未来予想図。
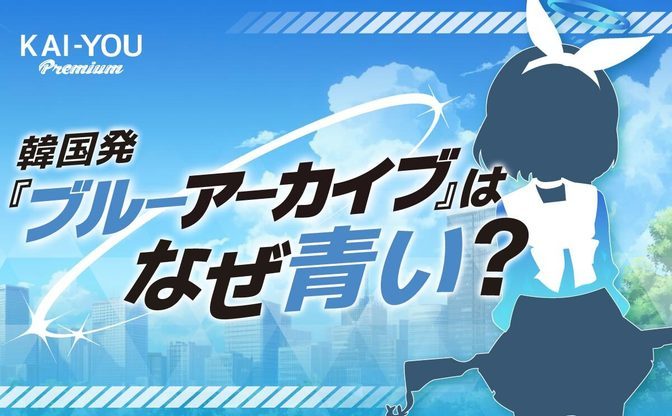
かつて「日本らしさ」と呼ばれた文化がアジアで共有され、新しい未来を形づくりつつある姿「ACGカルチャー」。
ACGカルチャーが産んだ『ブルーアーカイブ』の特別なものの正体。そして当人たちはほとんど意識しないまま影を落とす、韓国独自の価値観。

2017年から始まったVTuberシーンには、一世を風靡しながら瓦解していった、時代のあだ花とでも言うべきプロジェクトも数多く存在する。
「どのような契約形態、制作体制だったのか」「当時の人気や批判をどう受け止めていたのか」「なぜプロジェクトは頓挫しなければならなかったのか」いま、楪帆波の口から語られる、炎上の舞台裏。