KAI-YOU Premium 1周年 「個の時代」や「越境性」…そのテーマを振り返る
2020.03.31
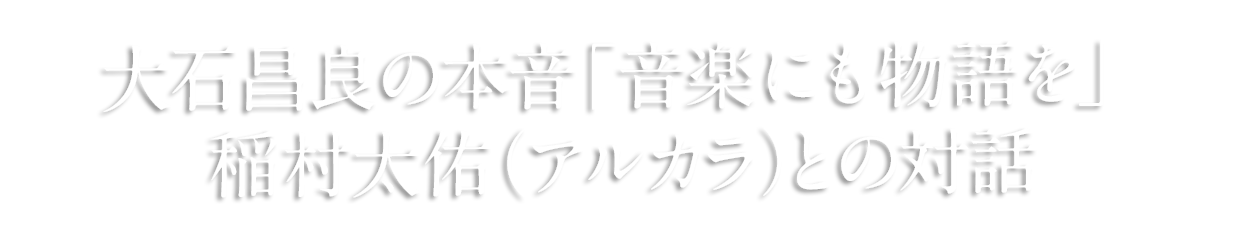
切った張ったのメジャーレーベルとも異なる、ライブハウスに根付く独立独歩のインディーズシーン。
アルカラ・稲村太佑の何気ない一言がその感覚を十全に表現している。
稲村太佑さんがギター・ボーカルをつとめるアルカラは年間100本以上のライブをこなすこともあるライブハウスバンドだ。加えて近年では、地元・神戸でネコフェスというサーキットイベントも主催し、日本のライブハウス文化を牽引する大きな存在になっている。
彼らの牽引してきたバンドシーンについては大石昌良さんの口からも前回語られた通りだ。
その活躍は音楽を辞めかけた大石さんを踏みとどまらせるきっかけとなっていたというドラマも明かされた。しかし同じように、大石昌良の存在もアルカラの活動方針に大きな影響を与えていた。
そして、二人の語るライブハウス史、ライブハウスイズム。
ホスト:大石昌良 ゲスト:稲村太佑 取材・執筆:オグマフミヤ 撮影:I.ITO 編集:新見直
目次
- 貫くライブハウスイズム
- アルカラは日本で一番変なことするバンド
- バンドシーンに再び並び立つ
大石 ライブハウスの文化は芸能界とも違って、ある種ガラパゴス化しているとも言えるよね。
稲村 ガラ…パゴス化?
大石 独自の生態系を築いているというか。今のようにメジャーにこだわらずインディーズで自分たちのレーベルを持ったり、個人事務所みたいな形で活動するバンドが増えてレーベルや事務所が後追いで声かけてくるような今の流れをつくったのは、アルカラから下の世代なんじゃないかな。
稲村 俺たちより前にもあったとは思うけど、徐々に多様化がはじまる時期だった気もする。
自分たちでマネジメントも全部やるってスタイルの確立はハイスタ(Hi-STANDARD)がはしりだと思っていて、同じようなメロディックやハードコアのジャンルにはそういうスタイルも徐々に浸透していた。
そこからポップとかロックとかやってる俺らの方にも広まってきて、インターネットの発達もあって、より決まった様式がなくなって、三國志でいうなら群雄割拠の時代になってきた感じがする。
※Hi-STANDARD 多くのフォロワーを持つ日本の伝説的パンクロックバンド。1999年に自主レーベルから発売したアルバム「MAKING THE ROAD」が100万枚以上を売り上げるなど数々の伝説を持つ

大石 昔はそれこそハイスタのような、際立った一握りの人しかやっていなかった、DIYで自分たちの活動をかっこいいものとして広めることを当たり前にしたのはアルカラだと思うよ。
アルカラにならえみたいな後輩バンドもいっぱいいると思うんだけど、そのアルカラが今でも地元の後輩バンドとかと対バンするのもスゴいよね。
稲村 俺らはライブハウスでのやり方を突き詰めてきたバンドだから、勢いついてキャパが上がろうが、逆に落ち着こうがやり方を変えることはなくて、Zeppでワンマンをやるようになったからといって、地元の二十歳の若手と対バンしなくなることはないよ。
大石 興行なんて結局動員数がすべてだから、会場は大きければ大きいほどよくて、逆もまた然り。
それでも小さいところでやり続けるって、ビジネスじゃないなにか、信念があってのことだろうから、それを貫く姿勢ってやっぱりカッコいいな。
続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です
今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう
残り 3487文字 / 画像5枚
800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題
KAI-YOU Discordコミュニティへの参加
メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も
※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。
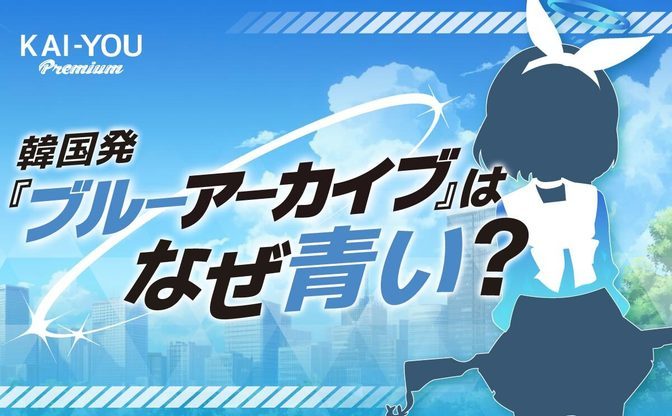
ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。