海の向こうのオタクは“闘争”を選んだ──韓国『ウマ娘』運営会社に「馬車デモ」で抗議した理由
2026.01.26
選挙をテーマにしたアトラスのRPG『メタファー:リファンタジオ』。
差別と憎悪が渦巻く多種族の社会は果たして存続できるのか。

クリエイター
この記事の制作者たち
2024年10月11日から、筆者の家のPlayStation 5は長時間の苦行に晒されることになった。この日、アトラスから発売された『メタファー:リファンタジオ』が発売されたからだ。筆者が在宅中には筆者が、不在時には長女が延々と『メタファー』をプレイし続けた。
『メタファー』はどうやらゲーム機本体への負荷が高いらしく、ボス戦などのシーンではオーバーヒートのせいで電源がよく落ちた。途中からは保冷剤でPS5を挟むようにしたことで、安定してプレイできるようになった。しかし、最近購入した別のタイトルでは、この方法でも落ちまくるので、ついに外付けの冷却ファンを購入した。その活躍に期待である。
かような障害はあったものの、我が家で『メタファー』は大好評だった。僕よりもプレイ時間の長い長女はずっと早くクリアし、そのあとしばらくはロス状態に陥っていたほどだ。ちなみに彼女の推しは、キャラクター人気投票の中間報告(1月末発表)で主人公を押しのけて一位となったイケメンキャラ・ストロールである。
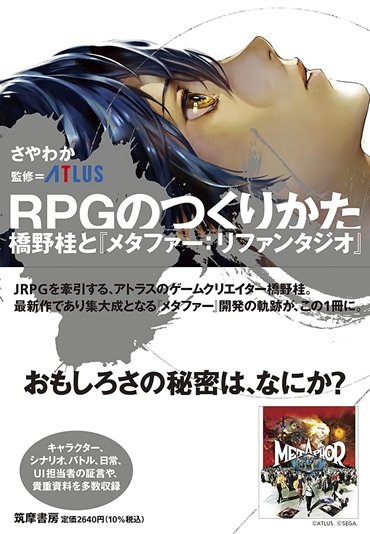
『RPGのつくりかた ――橋野桂と「メタファー:リファンタジオ」』書影/画像はAmazonより
さて今回は、政治や社会の研究者としての立場から『メタファー』について書こうと思う。その意味では、通常のゲームレビューとはかなり異なる内容である。この作品について理解するうえで参考になるのが、さやわか著・アトラス監修の著作『RPGのつくりかた 橋野桂と「メタファー:リファンタジオ」』(筑摩書房)である。大人数のスタッフが関与する大作ゲームがどのようにして制作されるのか、この作品がいかなる問題設定のもとで生み出されたのかを知ることができる。
この著作に登場する本作ディレクター橋野桂によれば、「基本的にアトラスのゲームって、たとえ現代劇であっても、何らかのメタファーになるものを入れようとしている」という(p.454)。実際、『メタファー』はまさに現実世界を彷彿とさせる主題、すなわち「選挙」を扱っており、さらに付け加えるとすれば「差別」と「不安」が重要なテーマとなっている。差別と憎悪が渦巻く多種族の社会は果たして存続できるのかが問われているのだ。
現実世界でも、これはきわめて難しい課題である。米国では人種間対立が深刻な水準にあり、欧州でも異なる宗教や文化をもつ移民や難民に対する排斥運動が激しさを増している。やや時代をさかのぼれば、1990年代に深刻な民族間対立が発生し、国家自体が解体した旧ユーゴスラヴィアのような事例まである。日本でもエスニック・マイノリティへの敵意が燃え上がることは珍しくなく、近年ではソーシャルメディアを中心としたクルド人排斥が目立つようになっている。
もちろん、フィクションである以上、現実の出来事とそのままリンクしているわけではないし、そこにはプレイヤーごとの解釈の余地が多分にある。したがって本稿は、あくまで筆者個人の観点からみた「本作が現代社会に問いかける問題とは何か」を論じるものだ。
なお、本稿の性質上、ネタバレに踏み込まざるをえない部分がある。しかし、発売後まもない作品であることもあり、ストーリーの根幹部分には触れない。なので、本作をまだプレイしていない、クリアしてない方であっても、少々のネタバレを許容していただけるのであれば、読んでいただいても差し支えないはずだ。
目次
- 『メタファー』の作品世界
- 『メタファー』にみる境界線の政治:身分、宗教、富、種族
- 「ニンゲン」の脅威と結びつけて語られた少数種族
- 「実力」さえあれば種族を問わない――ルイによる境界線の超え方
- キャゼリナがたどり着く教育という処方箋――パリパス族を待つ3つの可能性
- ストロールが体現するノブレス・オブリージュによる境界線の克服
- 主人公たちが示す「不安との向き合い方」
- 「幻想」の持つ力を信じること、理想を語り続ける必要性
- 対立はなくならないし、なくなるべきでもない『メタファー』世界とわれわれの未来
本論に入る前に、『メタファー』の作品世界について簡単に紹介しておこう。
『メタファー』の舞台となるのは、ユークロニア連合王国である。3つの国から構成されるこの連合王国は、幾度かの戦乱を経て統一され、現在は国王と元老院により統治されている。
さらに、この作品には9つの種族が登場する。それらのなかには政治的、社会的、経済的に優位な立場にたつ種族もいれば、差別や貧困に苛まれる種族も存在する。この世界の住人にとって種族の違いはきわめて重要で、どの種族に生まれるかによって人生が決まってしまうとされる。
なお本作の主人公は、もっとも差別を受けているとされるエルダ族に属している。主人公の故郷であるエルダ族の集落は焼き討ちに遭う過去を有し、ゲーム序盤でも街中を歩いているだけで差別的な言葉を投げかけられる。また、パリパス族も激しい差別にさらされてきた種族であり、作中ではその過酷な運命の断片が様々なかたちで描かれる。

歩いているだけで差別的な言葉を投げかけられる。/以下ゲーム画像は、すべて筆者によるスクリーンショット
もっとも、この作品世界において人びとを隔てる境界線は種族だけではない。1つは身分の違いだ。貴族や王族が存在する一方で、それに付き従う平民や奴隷も存在する。
もう1つは宗教の違いである。ユークロニア連合王国の国教は惺教(せいきょう)と呼ばれる宗教で、国民の大多数により信仰されているだけでなく、その教えを司る惺教府は政治にも大きな影響を行使する存在とされる。
そして、もう1つの境界線は、言うまでもなく富の格差だ。豊かな生活を享受する層がいる一方で、都市のスラム街では貧困に苦しむ人びとが数多く生活している。まとめると、以下の4つの境界線があると言える。
種族
身分
宗教
富
ただし、これらの境界はばらばらに存在しているわけではない。連合王国で最大の人口を誇るクレマール族、身体能力に優れるルサント族、知能に優れるイシュキア族は、身分、宗教、富のそれぞれにおいて有利な立場にあるようだ。他方、パリパス族やユージフ族、異教を信仰するムツタリ族といった身体的特徴が際立つ種族は、低い社会階層に甘んじ、貧困に苦しむ様子も描かれている。
本作の物語は、かつて種族間の平等を目指した国王ユトロダイウス5世が暗殺されるところから始まる。国王の実子が行方不明となっていることから、後継者をめぐる争いが勃発しそうになる。ところが、国王が生前に行使していた魔法が発動し、次の国王は民衆の信託をもっとも集めた者にするとの宣言がなされる。つまり、「選挙」で選ばれた者が次の王になるというのだ。そして主人公たちは、数奇な運命に導かれながら、この「選挙」を戦うことになるのである。
本作における境界線の設定についてやや詳しく述べたのは、現実世界においても、政治と境界線とはきわめて深く結びついているからだ。ここではまず、先に述べた身分、宗教、富、種族をめぐる境界線について、現実との関連で論じてみたい。
続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です
今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう
残り 10106文字 / 画像20枚
800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題
KAI-YOU Discordコミュニティへの参加
メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も
※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。
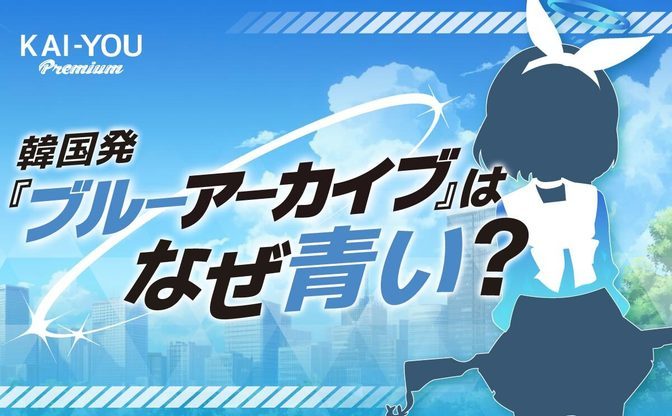
ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。