Vol.4 進化するバーチャルカルチャーの現在と未来
2019.09.26
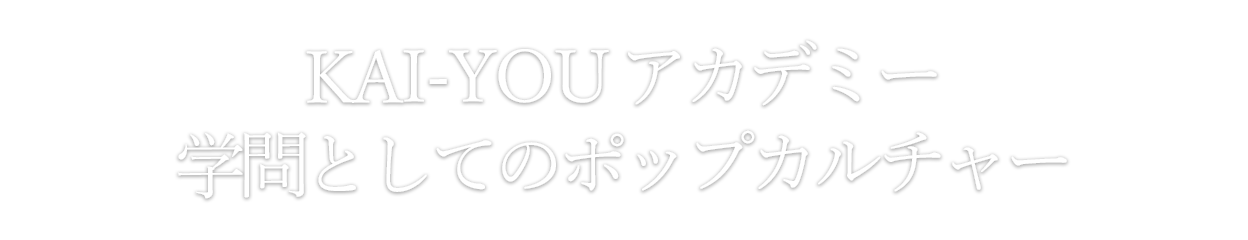
VTuberや仮想空間のアバターなど、現代の“仮面”は私たちの社会ではどのように位置づけられるのか。
カメルーンの民族社会に存在する秘密結社と接触して現地取材・研究を行ってきた文化人類学者の視点から、解き明かす。

クリエイター
この記事の制作者たち
「顔面は人の存在にとって核心的な意義を持つものである。それは単に肉体の一部分であるのではなく、肉体を己れに従える主体的なるものの座、すなわち人格の座にほかならない」──哲学者・和辻哲郎は「面とペルソナ」の中で、社会と文化における「面」の役割を説いた。
現代の“面”の現象を見つめる雑誌『面とペルソナ20's』は、コロナ禍を経験した2022年に創刊された。本稿では、「アバターと仮面、その狭間」を特集した『面とペルソナ20's』2号所収のインタビューを掲載。
VTuberやメタバースにおけるアバター、SNSのアイコン画像など“仮想世界における面のようなもの”とは何なのか?
前編に引き続き、カメルーンの秘密結社をフィールドワークした人類学者・佐々木重洋氏に聞いてみた。
目次
- VTuber は「変身」というよりは、「分身」の一形態である
- バーチャルなら、「自我の同一性」から脱却できるかもしれない
- VTuberはなぜ、自己責任に偏ってしまうのか
──VTuber のアバターやSNSの顔アイコンなど、人々が仮想空間で“仮面のようなもの”を着けて交流する時代になりました。佐々木さんから見て、伝統的な仮面と比べたときに抱いた率直な気づき、感想があれば教えてください。
佐々木重洋 VTuber は「変身」というよりは、「分身」の一形態であると思います。自分の身体を用いた変身ではなく、仮想空間にもう一つの身体をつくり出す点が、いわゆる「モノとしての仮面」を用いた仮面活動とは異なる。
日本で「仮面」という言葉は「マスク(mask)」「ペルソナ(persona)」「おもて」などさまざまな異なる概念を一括して含んでいます。
「マスク」を物質的な何かで顔を覆ったり隠したりするもの、「ペルソナ」を人間の人格や社会的な役割を意味するものだとすると、VTuberやSNSにはペルソナの観点では伝統的な仮面ととても似たところがあると思います。普段の自分とは何か違う存在になる、それを演じるという要素です。
一方、VTuber的なアバターと、伝統的な仮面とではバーチャル空間と物質的な世界、活動する空間が違うため、変身をみんなで支える「共同性の質」がまったく異なるんじゃないでしょうか。
──共同性の質ですか。
佐々木重洋 伝統的な仮面が生きている社会というのは、お互いに素顔が見えている状態での交流、対面コミュニケーションを母体としているので、規模はそこまで大きくはならない。さらに、前提としてある程度の固定的な人間関係がある。家柄や住んでいる場所、生まれ育ってきた背景なども含め、お互いに誰なのかがわかっているわけです。レヴィ=ストロース流に言えば「真正な社会」※1に近いと言えます。
そんな社会でAさんが仮面を着けた時に、「この瞬間この人はAさんではなくなり、神様のような何かになっている」といった約束事をみんなで支えるわけです。今この人は神様をやってるから神様として見よう。仮面を外したから、もうこの人はAに戻ったんだな、と。お互いに知っている者同士の規模感だからこそ、社会的な約束事が共有されやすいし、破りにくい。そして約束を破った場合の制裁も、社会的に機能しやすいのです。
一方でVTuberとかSNSの場合は、活動できる空間の規模が果てしなく大きい。仮面の下の正体がどうなっているのかわからない人がいっぱいいる、不特定多数の空間です。情報はアカウント名ぐらいで、年齢も性別もわからない。場合によっては一部を把握できるかもしれませんが、すべては不可能です。
そうした空間でみんなで約束事を共有したり、「今この瞬間はAさんを別の◯◯としてみよう」といった切り替えを成り立たせるのは難しい気がするんですよね。普段のお互いの姿をよく知らないわけですから。
──お互いの素性を知っているような小規模なコミュニティじゃないと、憑依や変身といった超常的な力をみんなで支えられない、と。
佐々木重洋 あとは、五感で感知する情報量の違いも大きいでしょう。顔アイコンに比べるとVTuberのアバターのほうが、3次元的な情報があったり、モーションキャプチャーで実際の人間と同じ動きをしたりと、より現実に近いかもしれません。それでもやはり物質世界、生身での交流のほうが、空気の流れとか匂いとか、五感で受け取れる情報量が今の時点では圧倒的に多いです。
人間が「モノとしての仮面」を着けて人前に出るとき、その身体性も大きな意味を持ちます。仮面は表情がなく動かないけれど身体は動いているという「生と死」が同時に現出する。これが、見る人びとに独特の当惑や驚きを与える理由の一つ。ただし、その力の及ぶ範囲はこの物質性がゆえに比較的狭く、活躍の場は小規模な社会、つまり「真正な社会」に限定されるように思います。
伝統的な仮面はその物質性ゆえに、着用した人間が狂気に走ること、異常な状態に陥ることを時間的にも空間的にも限定してくれるのです。
※1 真正な社会 文化人類学者のレヴィ=ストロースが唱えた概念で、「3 3万の人間は、500人と同じやり方では一つの社会を構成することはできない」ということから、対面的なコミュニケーションを基本とした、一人の人間が他の一人に具体的に理解される小規模な社会を「真正な社会」、間接的なコミュニケーションによる大規模な社会を「非真性な(まがいものの)社会」と区分した
──仮想空間のアバターや顔アイコンは、物質性をともなう「モノとしての仮面」に比べると、憑依や変身をみんなで共有すること、また超常的な力の暴走を防ぐことが難しい、という話でした。一方で、これらアバターやアイコンに、佐々木さんが感じているメリットはありますか?
佐々木重洋 より自由な冒険ができるところですね。違う自分をいくつも持てるし、しかもその相手が無限に広がっていることで、自分なりの生活空間、活躍の場を多様にいくつもつくることができる。それはおそらく、これまでの人類が経験していない出来事なんですよ。アバターはバーチャル空間でしかできない、自分の可能性や生活世界を拡大するすぐれた発明だと思います。
また、違う自分になれる変身の容易さは、バーチャル空間のほうが高い。仮面によって複数の自分を使い分ける、自分を多様化するなんてことは、伝統社会ではなかなかできません。お面を着けるときは神的なものになるなど、用途が限られていますから。
そのように神様に限らずいろんな自分になれるとなると、近代以降に人々が押し付けられてきた「自我の同一性」から脱却できます。
続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です
今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう
残り 3876文字 / 画像4枚
800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題
KAI-YOU Discordコミュニティへの参加
メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も
※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。
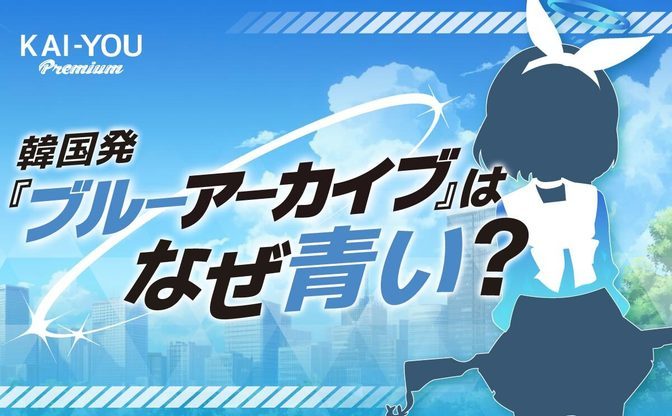
ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。