VTuber総数は2年連続横ばい、ファンダムは拡大で活況続く──「VTuber統計レポート2024」解説
2025.02.20
彼の思想は、たいていの場合私たちが気づかないうちに、私たちの世界観を方向づけている。
──アンヌ・ソヴァージョ
『機動戦士ガンダム』のテレビ放送が始まった1979年、その後の日本社会やサブカルチャーに大きな影響を与える邦訳書が刊行されている。フランスの社会学者、ジャン・ボードリヤールの『消費社会の神話と構造』(1970)である。
ボードリヤールは、人々がモノ(商品)を使用価値や交換価値によってではなく、自身のアイデンティティなどを示す「記号」として消費する社会システムを批判的に分析した。高度経済成長を経て大量消費社会を迎えたバブル前夜の日本では、折からのニューアカ・ブームも手伝って広く読まれ、最新流行のマーケティング理論として実装されていく。セゾングループ総帥・堤清二がボードリヤールに触発されて「無印良品」を立ち上げ、批評家・マンガ原作者の大塚英志が『物語消費論』(1989)を書いたのは有名な話だ。
それから40年あまりが過ぎ、2025年4~6月にガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』(ジークアクス)が放送された。制作の中核を担ったのは、監督の鶴巻和哉(1966–)や庵野秀明(1960–)、脚本の榎戸洋司(1963–)ら、いずれも『ガンダム』を「10代の多感な時期に観ている」(※1)1960年代生まれのクリエイターたちだ。本家『ガンダム』の「仮想戦記」を掲げ、いわゆる「正史」からのおびただしい引用やパロディ、オマージュがちりばめられた『ジークアクス』は、往年のガンダムファンを中心にSNSなどで大きな反響を呼んだ。
しかしその半面、過剰なまでのパロディに違和感を覚えたり、キャラクター造形や物語展開に疑問を抱いたりした視聴者も少なくない。たとえば批評家の杉田俊介は、物語中盤の戦闘描写について次のような感想を漏らしている。
ジークアクス7話、戦闘に巻き込まれて民間人の死者が結構出ているはずなんだけど、そういうことが一切描かれないのが気になる。相変わらず情報過多でハイコンテクストではあるんだが、視聴者も戦争ごっこ、考察ゲームをひたすら楽しむだけになってしまうというか…杉田俊介(@sssugita)による2025年5月21日のXへの投稿
安彦良和氏に連続インタビューした時、ガンダム史にはやたら詳しいが、現実の歴史には関心がない、そうしたファン層を作ってきた責任が自分たちにはある、という様なことを話されていた記憶がある。ジークアクスでそれを思い出す。例えばガザの映像とアニメを行き来しうるオタク的感性があるはずでは?杉田俊介(@sssugita)による2025年5月23日のXへの投稿
『ジークアクス』第7話では、テロリストの搭乗する巨大なサイコガンダムが、主人公のマチュやニャアンの住む宇宙コロニーで暴れ回る。ところが、杉田の言うように民間の死傷者などは一切描かれず、テロリストもあっさりと撃退されて事態は収束。物語の舞台はコロニーから月、地球へと移り変わっていく。
富野由悠季(1941–)や安彦良和(1947–)らが手がけた『ガンダム』が、戦争に翻弄される人々の苦悩や悲哀を徹底して描いてきたことを踏まえれば、杉田の違和感は理解できる。事実、毎週のように「考察ゲーム」に興じていたファンたちも、第7話予告の時点ではマチュの母親やニャアンの知人がテロに巻き込まれて命を落とし、少女たちに戦争のトラウマを植えつけるのではないかと予想していた。
ところが『ジークアクス』は、そういったある意味で「ガンダムらしい」展開をことごとく裏切り、鶴巻や榎戸の得意とするボーイ・ミーツ・ガールの物語として進んでいく。その好き嫌いは別にしても、杉田の指摘する通り、2つの作品のあいだには「戦争」をめぐる、というよりも「戦争を描くこと」をめぐる決定的な断絶が走っているように見える。
「ガンダム史にはやたら詳しいが、現実の歴史には関心がない」オタクたち──そこには『ジークアクス』の制作陣も含まれるだろう──に、富野や安彦はいらだちを隠そうとしない。彼らにしてみれば、本作は『ガンダム』の商標や意匠を好き勝手に「サンプリング」した悪ふざけ、あるいは「戦争ごっこ」にしか見えないかもしれない。
この断絶をどう理解したらいいだろうか。1940年代生まれの富野・安彦と、60年代生まれの庵野・鶴巻・榎戸の世代の違いといえばそれまでだが、そこにはもっと根本的な、言ってみれば「時代精神」のズレがあったのではないか。そしてこのすれ違いは『ガンダム』が放送された1979年の時点で、すでにどうしようもなく運命づけられていたように思う。
※1 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- “MATERIALS“』、バンダイナムコフィルムワークス、2025年、7頁。
目次
- テレビゲーム戦争:湾岸戦争とボードリヤールの視線
- 「盗め」「サンプリングせよ」──シミュレーショニズムとガンダム
- “コピー世代”の宿命──庵野、鶴巻たちの時代精神
- ジオンはアメリカだった? シミュレーションされた戦後日本
- 偽物の重力と海の世界で──マチュの情念と「出口」
- 本物の“キラキラ”と、極上のシミュラークル『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』
手がかりになりそうなのは、冒頭で触れたジャン・ボードリヤールだ。
日本では消費社会論で脚光を浴びたボードリヤールだが、太平洋を隔てたアメリカでは「ポストモダニズムのグル(導師)」として注目を集め、1980~90年代にかけてカルト的な影響力を持った。とくに悪名高いのは、1991年の湾岸戦争終結後に刊行された『湾岸戦争は起こらなかった』というイカれたタイトルの本だ。
戦争勃発直前に「湾岸戦争は起こらないだろう」と題した論評を仏リベラシオン紙に寄稿したボードリヤールは、あてが外れて多国籍軍による攻撃が始まると「湾岸戦争はほんとうに起こっているのか?」を立て続けに掲載。挙げ句の果てに「湾岸戦争は起こらなかった」を発表して多くの知識人の顰蹙を買う。
だが、史上初の「テレビゲーム戦争(ニンテンドー・ウォー)」と呼ばれた湾岸戦争が、従来の戦争のイメージを大きく覆すものだったことはたしかだ。開戦の瞬間から多国籍軍による空爆がリアルタイムでテレビ中継され、モニタリングされた標的に精密誘導弾が命中するシーカー映像が次々と公開されると、まるで任天堂のテレビゲームのような画面に世界中の「視聴者」が啞然とする。そこで人々が目にしたのは「戦争」というよりも、むしろ徹底的にコンピュータ制御された「戦争のシミュレーション」であり、映像メディアに媒介された「出来事の疑似餌」だった(※2)。
ボードリヤールは『象徴交換と死』(1976)や『シミュラークルとシミュレーション』(1981)といった著書のなかで、シミュレーションを現代の支配的な「シミュラークル」として位置づけている。これは「まがいもの」や「似姿」を意味し、もともとはプラトンのラテン語訳に由来する言葉だ。
ボードリヤールによれば、本物と偽物、オリジナルとコピー、現実と幻想といった古典的な記号秩序は大量生産(オリジナルなきコピー)によって乗り越えられ、そしていまやシミュレーション・モデルが現実それ自体を作り上げる。現実は「模倣」されるのでも「表象=代理」されるのでもなく、二進法的なコードに基づいて産出される差異表示記号としてのシミュラークル=シミュレーションに置き換えられていく──「シミュレーションとはオリジナリティもリアリティもないリアルなモデルで形作られたもの、つまりハイパーリアルだ」(※3)。
まるで映画の『マトリックス』(1999)みたいな話だ、と思っただろうか。それもそのはず、監督・脚本のラリー&アンディ・ウォシャウスキー兄弟(1965–/67–、現在は性転換して姉妹)はボードリヤールの強い影響下で『マトリックス』を制作し、作中には印象的なガジェットとして『シミュラークルとシミュレーション』まで登場する──もっとも、著者自身は「誤解されている」として映画には批判的だったが。これも映画ファンのあいだでは広く知られた話だ。
『ジークアクス』もまた物語が進むにつれ、鶴巻らと同世代のクリエイターが手がけた『マトリックス』とよく似た設定の作品であることが明らかになる。マチュやニャアンの世界は、正史にも登場するニュータイプの少女・ララァが、ガンダムに敗れて死ぬ恋人のシャアを生かすために作り上げた「夢」の世界のひとつ、つまりはシミュレーションだった。ちょうど『マトリックス』における「現実」が、人間をエネルギー源とする機械によってシミュレートされた仮想世界にすぎなかったように。
こうしたメタフィクショナルな設定は、作中のリアリティへの期待値をひっくり返してしまう。『ジークアクス』が「戦争ごっこ」にしか見えないとしても、それは物語世界そのものがひとりの少女の夢=フィクションなのだから、ある意味では当然のことだ。それどころか、戦後の大量消費社会に育ち、戦争のシミュラークルとして『ガンダム』に親しんできた世代にとっては、むしろ「ごっこ=シミュレーション」のリアリティのなさこそが、逆説的に最もリアルな表現なのかもしれない(※4)。
事実、ボードリヤールは湾岸戦争に際してこう語っている──「現実的なドラマ、現実的な戦争、そんなものをわれわれはもはや好まないし、必要としない。われわれに必要なのは、にせものの増殖と暴力の幻覚がもたらす催淫的な味わいである」(※5)。『湾岸戦争は起こらなかった』は刊行から30年以上が過ぎたいまも、ウクライナやガザをめぐる論評のなかで参照され続けている(※6)。
※2 ジャン・ボードリヤール「湾岸戦争は起こらなかった」、『湾岸戦争は起こらなかった』塚原史訳、紀伊國屋書店、1991年、121–122頁。
※3 ジャン・ボードリヤール『シミュラークルとシミュレーション』竹原あき子訳、法政大学出版局、1984年、1–2頁。ただし訳文を一部変更している。
※4 この記述は2025年7月8日にXのスペースで行われた「低志会」でのnoirseの発言に依拠している。以下のアーカイブ動画を参照。「【低志会】2025春アニメどうだった?」2025年7月13日。
※5 ボードリヤール「湾岸戦争は起こらなかった」、122頁。
※6 ガザについては、たとえばトルコメディアの以下の記事などに『湾岸戦争は起こらなかった』への言及がある。Kubra Solmaz, “Are the Gaza dead becoming another post to scroll across?,” TRT Global, November 8, 2023.
『ジークアクス』にちらつくボードリヤールの影は、作中世界の設定にとどまらない。『湾岸戦争は起こらなかった』が邦訳されるちょうど1カ月前、やはりこの思想家と関係の深い文化現象を紹介する書籍が出版されている。庵野らと同世代の美術批評家・椹木野衣(1962–)の『シミュレーショニズム』(1991)だ。
1980年代初頭、現代美術の中心地・ニューヨークでは、かつて流行した過去の様式を再びなぞるような奇妙な美術動向が生まれていた。それが「シミュレーショニズム」と呼ばれる運動だ。この名称はもちろん、当時刊行されたばかりのボードリヤールの著書『シミュラークルとシミュレーション』などに由来する(英訳は1983年)。
シミュレーショニズムの作家たちは、表現主義や幾何学的抽象、ポップアートなどの「古い」様式をシミュレートして別の文脈に移し替え、最新流行のアートとしてリサイクルした。なかでも極端な例がマイク・ビドロだ。ビドロは1980年代後半、ピカソの傑作の数々を実物そっくりに描き直し、《これはピカソではない》と題して自身の個展で発表。ほかにもセザンヌやマティス、ポロック、ウォーホルといった巨匠たちの作品の「再制作」を手がけ、オリジナリティをめぐる激しい論争を巻き起こした。
椹木はこうした実験的な試みをいくつも取り上げながら、ボードリヤールを下敷きに、シミュレーショニズムのマニフェストを次のようにまとめている。
恐れることはない。とにかく「盗め」。世界はそれを手当り次第にサンプリングし、ずたずたにカットアップし、飽くことなくリミックスするために転がっている素材のようなものだ。シミュラクルの問題を単なるノスタルジーの問題としてではなく、新たな前衛を構成するための武器として変形すること、あるいはシミュラクルのデジャ–ヴュをある種のユートピアへとむけて唯物論的に提示すること──椹木野衣『増補 シミュレーショニズム』、ちくま学芸文庫、2001年、116–117頁。
ここで語られている「サンプリング」「カットアップ」「リミックス」といった概念は、主に1980年代のクラブ・ミュージックなどで多用された方法論だ。ごく大雑把に言えば、サンプリングは既製品からの流用、カットアップは分解と再構成、リミックスは再編集を意味する。
椹木自身はシミュレーショニズムの新しさを強調するために、引用やパロディといった古典的な手法との違いを強調しているが、重要なのは手法そのものというよりも、それらが過去の様式を「盗む」、あるいはシミュレートするための手段として用いられることだ。そして一読してわかるように『ジークアクス』は、それが紛れもない「公式」であることを除けば、このマニフェストで謳われている要件をほぼ完璧に──おそらく本家・シミュレーショニズムの作家たちと同じかそれ以上に──満たしている。
テレビ放送に先立ち、一部エピソードを再編集した劇場公開版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』を初めて見た観客たちは、スクリーンに映し出された光景に目を疑った。スタジオカラーによる「新作」と聞いてきたのに、安彦によるキャラクターデザインから各種のサウンド、画面のレイアウトにいたるまで、往時の『ガンダム』を偏執的なまでにシミュレートした映像が流れ始めたからだ。
正史の主人公・アムロは登場せず、代わりにライバルのシャアが新規にデザインされた「ガンダム」に乗り込み、地球連邦を打ち破ってジオン公国を勝利に導く──。「こんなことが許されていいのか」というミーム画像がSNSで飛び交ったのはいまだ記憶に新しい。
『ジークアクス』はシミュレーショニズムよろしく、まさに『ガンダム』という「素材」を「手当り次第にサンプリングし、ずたずたにカットアップし、飽くことなくリミックスする」。正史では一度も実現しなかった少女の夢、あるいは「ユートピア=どこにもない場所(ou topos)」としての仮想戦記をシミュレートするために。「シミュラクルのデジャ–ヴュ」という言い回しは、何度も見たことがある(気がする)のに一度も見たことがない『Beginning』にこそふさわしい。
続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です
今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう
残り 5894文字 / 画像1枚
800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題
KAI-YOU Discordコミュニティへの参加
メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も
※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。
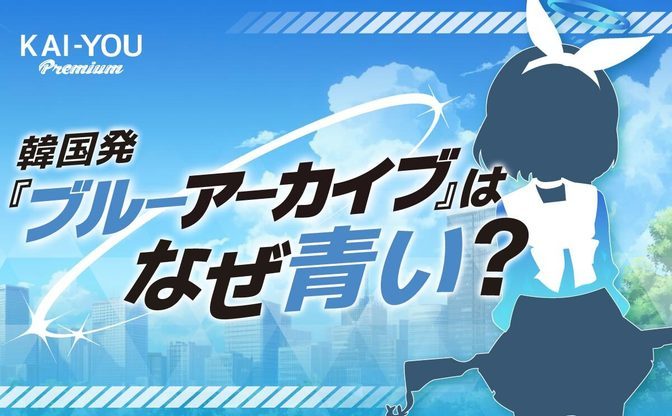
ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。