新時代の「メディアの王」YouTube担当者に聞いた、境界を越えることの責任
2020.10.23
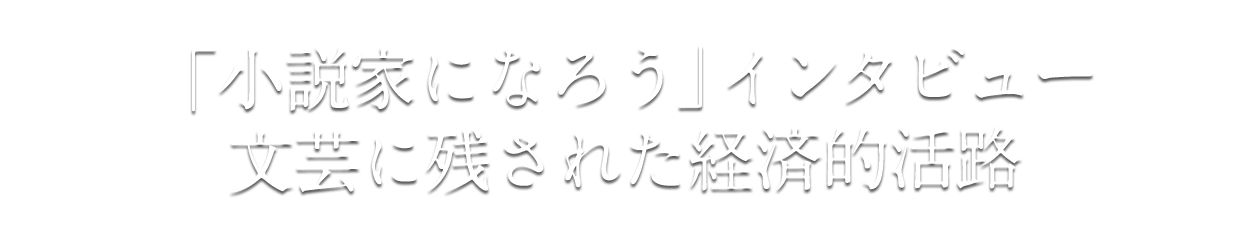
“Webで小説を読む”という新しい文化と、 “書籍化”を象徴とする既存の出版文化が、今後どのような関係を築いていくのか。
前回インタビューの「小説家になろう」から初の書籍化作品が登場したくだりと、合わせて読んでいただければ、開設から数年で“Webで小説を読む”文化が、どれだけ発展したかを感じることができる。
この記事は、下記連載記事の続きです。
「小説家になろう」の読み手が増大したのは2009年のリニューアルと、書き手の意識が変化した2011年の『魔法科高校の劣等生』『ログ・ホライズン』の書籍化が契機の一つだと、運営会社であるヒナプロジェクトの平井さんは言う。
これらの出来事を経て「小説家になろう」は閲覧数、登録作品数ともに日本最大級の小説投稿サイトとなった。
それも書き手は作品を、読み手も感想やコメントを自由に書き込めるオープンな場だ。人々が集まり、言葉を交わす以上、トラブルを招く可能性は否めない。これまで例を見ないほど膨大なユーザーや作品を抱えながら、サイトを無事運営するにあたって、スタッフたちはどのような指針をもって臨んだのだろうか。
また近年「小説家になろう」のユーザーの間では、実装されているランキングやアクセス解析が書き手同士の競争心を過剰に煽っているのではないかという指摘もある。
実際、閲覧数を気にするあまり、作品を未完のまま放置したり、筆を折ったりするユーザーも多く、その機能を疑問視する向きもある。それについて質問をぶつけてみると「プラットフォーム」という立場での、意外な答えが返ってきた。
目次
- 公平性を守るためにあえてしないこと、できないこと
- 開設当時の状況とランキング機能を導入した経緯
- 「小説家になろう」発の人気書籍が生まれるわけと出版社とWeb小説の関係
- プロの小説家が参加している現状と「小説家になろう」の矜持
──「小説家になろう」は投稿された小説が集まる、いわゆるポータルサイトという認識でいいのでしょうか。
平井 小説が集まるのは間違いありませんが、弊社では一貫してプラットフォームという呼称を用いています。
「小説家になろう」自体は、あくまで投稿者と閲覧者に場所を提供するサービスで、外部に広く情報を発信する立場ではないのでポータルサイトというと語弊があるかもしれません。コンテストなどを催すことはありますが、それはあくまでサイト内のユーザーに対しての告知なんです。
──プラットフォームとしての「小説家になろう」を運営するにあたり、心がけていることはありますか?
平井 基本的には、すべての作品に対してフラットな姿勢を保つことです。具体的には特定作品のPRは極力しない。たとえば運営側から書籍化した作品に向けて、お祝いの告知などもやろうと思えばできるのですが、もしやるのならばすべての書籍化した作品に行わないと公平さは保てない。だからやっていません。
それはアニメ化や映画化が決定した際にも同じことです。読者数の多い/少ないも関係なく、作品や著者に対してはフラットに向き合おうとしています。
──しかし「小説家になろう」内には出版作品紹介のページもあったと思いますが。
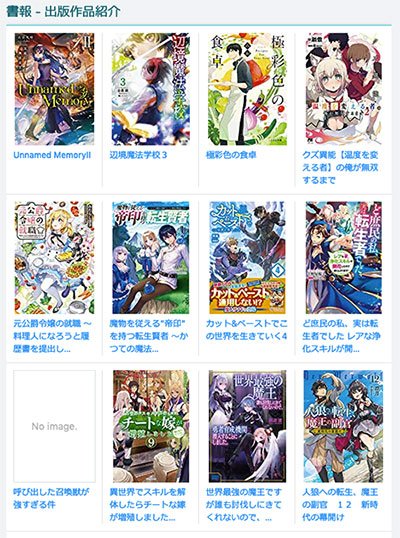
書籍化作品を紹介する「書報」は5月末のリニュアール以降、トップページにも表示されるようになった
山崎 あれは、あくまで「作者から申請があったものだけ」という条件つきの掲載なんです(外部リンク)。などで網羅しているわけではありません。
平井 他に、お便りコーナーというプロデビューを果たした作家さんからのコメントを載せるページもありますが、それも掲載するのは自主的に投稿していただいたものだけで、運営側から個別にアプローチすることはないんです。
もちろん、こちらとしてもユーザーにとって喜ばしいことであれば、お祝いしてあげたいという気持ちはあるので、投稿してもらうという形で協力させていただいています。
──サイトとしてのポリシーと、作家や作品を応援したいという気持ちの落としどころとしてできた機能ということですね。
続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です
今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう
残り 5376文字 / 画像1枚
800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題
KAI-YOU Discordコミュニティへの参加
メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も
※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。
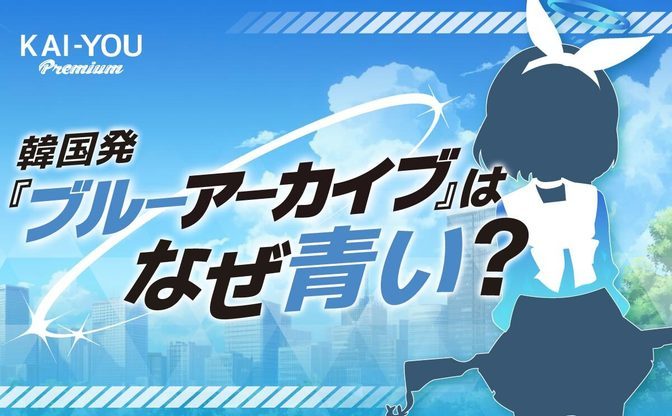
ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。