ゲームの画像解剖 ドット絵表現が生み出した構図たち
2020.02.07
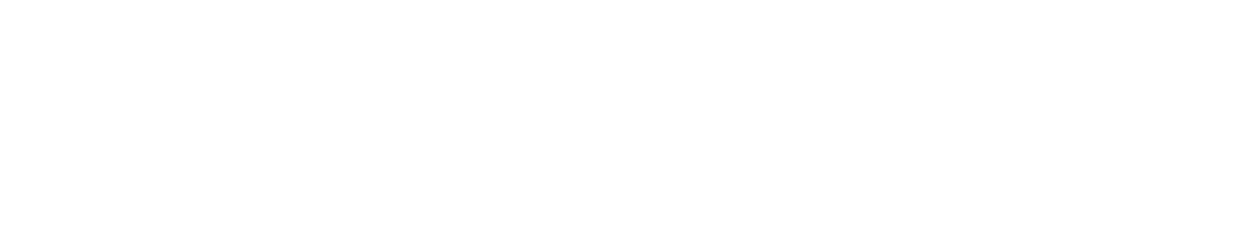
かつてないほど、多くの人類が、来たる未来に思いを馳せている今。
あり得たかもしれない未来について考え続けてきたSF作家は、どんな未来を思い描くのか。
このところ日本のSFが面白くなり、新しい作家との出会いを楽しんでいる。なかでも『SFマガジン』2020年8月号の特集「日本SF第七世代へ」で紹介された2010年代デビュー組の作家には、久しぶりに新しい波の到来を感じる。
その代表的な存在が樋口恭介と津久井五月だ。樋口は『構造素子』で、津久井は『コルヌトピア』で2017年の第5回ハヤカワSFコンテスト大賞を受賞している(両作ともこの6月に文庫化されたばかり)。この二人が『WIRED』日本版Vol.37の特集「SFがプロトタイプする未来」に揃って参加している。
『WIRED』日本版は1994年(同朋舎出版、のちにDDP)に創刊され、1998年にいったん休刊となった後、2011年以後はコンデナスト・ジャパンから復刊した。私は94年から95年にかけてこの雑誌の編集部に在籍していたことがある。
当時はまだウェブやITの草創期で、この編集部ではじめてウェブブラウザMosaicを立ち上げたときの新鮮な衝撃はいまもよく覚えている。それからすでに四半世紀を経て、いまこの雑誌が何を目指しているのかということにも、少なからぬ関心があった。
執筆:仲俣暁生 編集:新見直
目次
- 「未来をプロトタイプする構想力」としてのSF
- 技術と人間への信頼 藤井太洋がSF小説として描く未来
- 未来における“自然の役割”
- SF作家が夢想した、身体性を取り戻すための独立国家
- 未来のために、SFプロトタイピングが示したもの
この特集のバックボーンとなるのは、インテル社の未来研究員ブライアン・デイビッド・ジョンソンが2010年に提唱した「SFプロトタイピング」という未来予測の手法である。
この考え方に則り、樋口や津久井といった新鋭SF作家をはじめ、『ニムロッド』で芥川賞を受賞した上田岳弘、電子書籍のセルフパブリッシング作品『Gene Mapper』でデビューした藤井太洋、ネット小説サイト「カクヨム」に投稿した『横浜駅SF』で注目され、生物学者としての経歴をもつ柞刈湯葉といったプロの小説家にくわえ、ASSAwSSIN名義で映像演出家としても活躍するライターの吾奏伸、ウェルビーイング(人が良く生きている状態を指す「Well-being」)を専門とする予防医学研究者の石川善樹らが、実際にこの手法により「物語(ナラティブ)」を紡ぐという好企画である。
編集長の松島倫明は「EDITOR’S LETTER」で、この特集企画は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)がパンデミック化し始めるなかでスタートしたことを明かしている。
前回に検討したとおり、文芸誌や論壇誌ではこのところコロナウイルスにまつわる特集がこぞって組まれている。そのなかに『WIRED』日本版のこの特集を置くと、前回みた『SFマガジン』6月号でのSF作家の発言(そのなかには藤井太洋もいた)にも通じるポジティブな未来志向が顕著である。
松島は「EDITOR’S LETTER」に次のようなことも書いている。
未来をフィクショナルに構想するSFの力は、いつの時代も連綿と、新しい一歩を踏み出した人々の手によって実装されてきた。それは、人類が手にした稀有なツールだったのだ。だからもしいま、この日常が「結局は変わらない」ものだと思えるなら、そこに足りないのは、ぼくたちが未来をプロトタイプする構想力なのだ「WIRED」日本版Vol.37の特集「SFがプロトタイプする未来」 「EDITOR’S LETTER」より
SFというジャンルは「サイエンス・フィクション」として生まれたが、1960年代に英米で「ニューウェイヴ」と呼ばれる、ジャンル自身に対する内省的な動きが生まれると、SFの定義についてもさかんに議論されるようになった。その一つが、「SFとはスペキュレイティブ(思弁的)なフィクションである」というものだ。この理解に立つなら、仮説的な未来をプロトタイピングした「物語(ナラティブ)」がSFに近づくのは当然だろう。
では、彼らの構想力は、どんな未来を描いたのか。
特集の冒頭を飾るのは藤井太洋の「滝を流れゆく」。2020年の急性呼吸器症候群COVID-19の結果、人類は〈大隔離(ザ・クァランティン)〉と呼ばれる交流途絶の時代に入った。
VRステージの設計を専門とする主人公の斯波紫音は、2020年に大学に入学した世代。卒業後は父方の郷里・奄美大島に移住し、VRデザイナーとして生活している。そこで出会った夫婦と小さな子どもからなるアジア系の家族との心の交流が描かれた短編だ。
プロトタイピングという視点からみたとき、まず注目すべきは「抗体タトゥー」というテクノロジーである。正式には「抗原抗体反応証生身体印章」と呼ばれる「抗体タトゥー」は、抗体が有効である間だけアイコンが輝く。このアイコンを示すことで、接触してよい相手かどうかを人と人はお互いに確認できるのである。
この小説に描かれる2030年代の世界では、ほかにも藤井のデビュー作『Gene Mapper』のモチーフともなった遺伝子編集やVR技術による空間設計(ステージング)が実装されており、それぞれがこの「物語」のなかで重要な役割を占める。
藤井太洋の小説は、技術が切り開く可能性と、人間が本来的にもつ「公正性」の双方を信頼することで希望のある未来を描く、というモチーフが一貫している。本作に限らず、藤井の一連の作品を「SFプロトタイピング」の観点から高く評価することは妥当に思える。
続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です
今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう
残り 3146文字 / 画像2枚
800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題
KAI-YOU Discordコミュニティへの参加
メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も
※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。
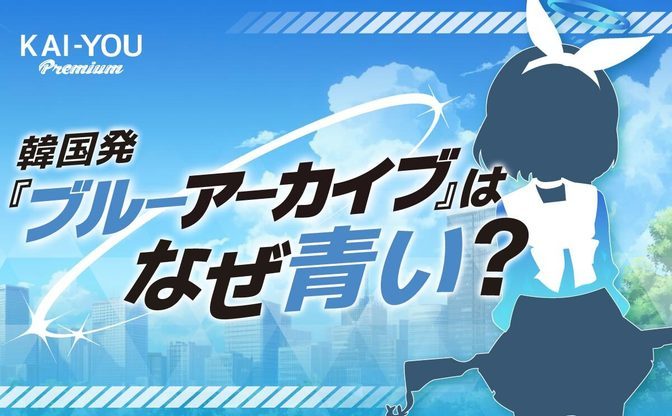
ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。