本棚から見える『バケモノの子』の世界 細田守は『白鯨』で何を伝えたかったのか
2020.02.18
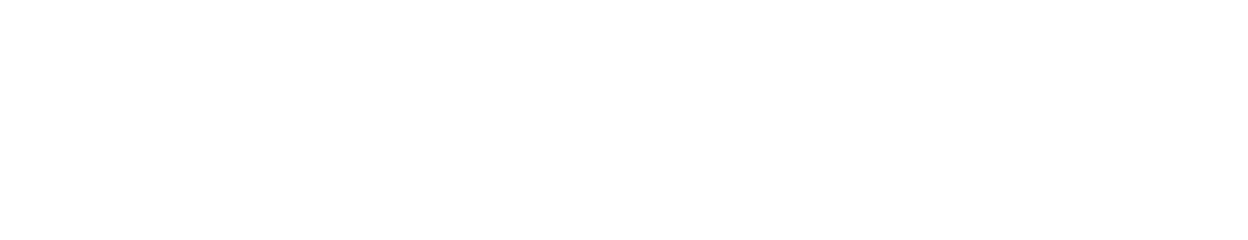
そもそも『未来のミライ』は監督の個人的体験の反映を目的とした作品であり、偶発的でもなければ、自己顕示欲の発露でもない。細田監督は、劇中でお父さんがお母さんから言われたセリフが、自身が奥さんから言われた言葉であることを明かしている。
むしろ『未来のミライ』を「私小説」と考えてみたらどうだろう。「私小説」は自らの体験を素材に、虚実を取り交ぜて創作物とする表現だ。その手法は、明治末期から昭和初期の日本近代文学のなかで積極的に用いられてきた。
『未来のミライ』もまた、細田監督の個人的な経験を、現実と空想を絡めながら表現した作品なのである。むしろそれに注力した。そこにアニメーションを使うことが、時代の変化と言えるだろう。

記者発表での細田守監督とスタジオ地図のプロデューサー齋藤優一郎さん/写真はKAI-YOU編集部撮影
一方で、アクションやアドベンチャーをもっと期待していたという声もある。それは『時をかける少女』や『サマーウォーズ』のようなハラハラドキドキするエンターテインメントなのかもしれない。
もちろん細田監督は今回も、『時をかける少女』や『サマーウォーズ』のような作品をつくろうとすればできたはずである。ファンのニーズがそこにあることも知っていたかもしれない。しかし、それを選ばなかった。
その理由を知るにはスタジオ地図の設立の原点に戻る必要がある。スタジオ地図の公式サイト内の“「スタジオ地図」とは”と題したメッセージには、次のような一文がある。
東映長編やディズニー作品などアニメーション映画の歴史は長くありますが、まだまだやっていないモチーフやテーマ、そして表現の可能性は無限に拡がっています。その可能性というフロンティアに向かって、大海原に船出した冒険者たちのように主体性と覚悟、チャレンジ精神を持って挑んでいきたい。そして誰も見たことがない映画という新大陸を見つけ、その真っ白な大地に新しい地図を描いていきたい。「アニメーション映画制作会社『スタジオ地図』とは」より抜粋
アニメーションの表現でまだ描いていないもの、真っ白な地図に自分たちが描きこむもの。『未来のミライ』に登場した「4歳の男の子の主人公」「小さな家の中にほとんど限定された舞台」「自らの体験の取り込みと積み上げ」、そのすべてがまだ描かれていないものなのである。
海外ではこうした作品の新しさと挑戦が評価されている。
なぜ日本と米国でこれほどまで評価の違いが生まれたのだろう。
日本ではこれまでのような作品を期待する観客との間にギャップがあったことが大きい。とりわけ映画宣伝において、これまでのヒット作のイメージを積極的に活用したことが、作品本来の持ち味とのギャップを広げた。
一方の米国では、細田監督の知名度はさほど高くなかった。海外での人気はフランスなどの西ヨーロッパ、あるいは東アジアが中心だ。米国では『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』などが公開されていたがいずれも小規模。作品に接する機会が少なく、名前も他の地域に比べるとあまり知られていなかった。
結果的に、そんな知名度の低さが幸いした。現地の観客は、日本のような固定化された細田作品のイメージがなく、真っ白な状態で『未来のミライ』を観ることができた。
加えて、配給を担当したGKIDSの役割も大きかった。もともとインディペンデントや海外の良質なアニメーションを届けてきた会社だ。ハリウッドのメジャーな配給会社を除くと、アニメーション部門において最もアカデミー賞へのノミネートを送り出しており、この分野では名門とみなされている。
GKIDSを通すことで『未来のミライ』という作品の文脈は、よりふさわしいかたちで、ふさわしい観客に届いた。むしろGKIDSのファンの期待に対して『未来のミライ』はぴったりだった。これが米国で特に評価が高い理由だ。
夏休みの一大エンターテインメントを打ち出した日本とは大きく異なる。

『未来のミライ』を巡る議論は、日本のアニメーション界にある問題を浮き彫りにしている。それは宮崎駿作品を中心としたスタジオジブリの存在感の大きさだ。
2013年に宮崎駿監督が引退宣言(2017年引退撤回)したあと、日本の映画界では誰がそのポジションを引き継ぐのかが課題になった。宮崎監督とスタジオジブリが生み出す巨大なビジネスを失うわけにいかないからだ。大ヒットを連発してきた細田守監督に、その期待がかかるのは自然な流れだった。
しかし細田監督と宮崎監督は同じではない。作品を世に送り出すにあたり、これまでのスタジオジブリのようなスタイルを期待し、宣伝を踏襲すればズレが生じるのは当然だろう。
エッセイのようにエピソードを連ねていく『未来のミライ』には文学的なところがある。本来であれば、宣伝においてもその持ち味にフォーカスすべきだった。この作品にふさわしい人々に届いたはずだ。
仮に文学路線で『未来のミライ』を世に届けたら、作品の持ち味はより伝わったかもしれない。一方で、28億円を超える大きな興行収入を実現できたかどうかはわからない。夏休みの大型劇場アニメには、アドベンチャー、アクション、ファンタジーがもっともっと求められるからだ。
興行成績だけを考えれば、今回のマーケティング戦略は正しかった。しかしその戦略は本来の『未来のミライ』、そして細田守監督との間にジレンマを生んでしまった。その点では今回の宣伝戦略は失敗だ。
結局は何が正しかったのかはわからない。ただ確かなのは、作品本来の持味に対する海外での高い評価は、細田守監督の次の一歩に確実につながったことだ。
細田守監督の次の作品は、きっと何年後かに登場する。次回作も間違いなく、真っ白な地図に描かれる新たな挑戦になるはずだ。
そのときはあまり縛られることなく、自由に観るのがいい。きっとそのほうが作品を楽しめるに違いない。
クリエイター
この記事の制作者たち
※この記事は期間限定でプレミアムユーザー以外にも開放されています。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。

ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。