目指すべきコンテンツの在り方と、その敵
2020.05.22
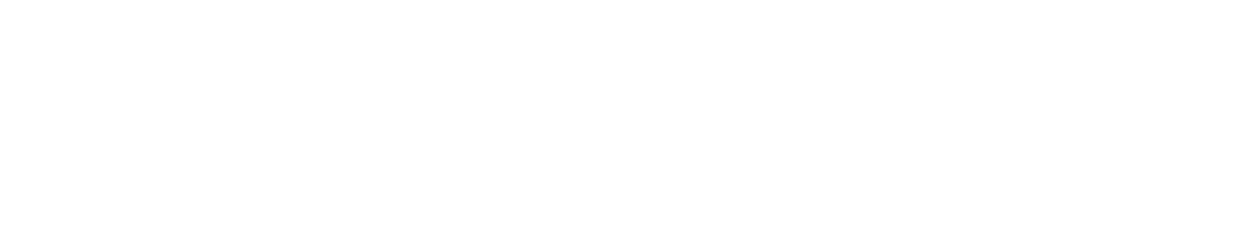

クリエイター
この記事の制作者たち
VTuberの九条林檎さんを迎えて、界隈のホットなトピックを解説してもらう連載「おしえて、九条林檎様!」。第11回のテーマは生成AIとファンアートです。
VTuberシーンにおけるファンアートの中でもイラストの制作は非常に活発です。VTuberそれぞれのファンアート専用ハッシュタグを調べれば、推しへの愛が描き込まれた作品を山のようにSNSで目にすることができます。
その中からVTuberが内容に合うイラストを配信のサムネイルなどに利用するケースも珍しくありません。ファンとVTuber、双方にとってwin-winの関係が、一種の文化としてVTuberシーンには定着しています。
ただし、採用したファンアートがトレパク(※1)だった、などの潜在的リスクもあります。九条林檎さんご自身も巻き込まれたという、盗作イラストがファンアートとしてSNSで公開され、配信のサムネイルになってしまうケースもあります。
そして近年、生成AIの普及に伴い、AIイラストの問題も加わりました。大神ミオさんがAIイラストだと指摘されたイラストをサムネイルに使用していたことをきっかけに、騒動に発展(当該イラストレーターはAI利用を否定)して耳目を集めました。
ファンアート起用へのリスクが高まる中、同人文化と強く結びついて発展してきたVTuberシーンはどう変化していくのか。騒動に巻き込まれた時の対処法は? ご自身もファンアートを巡るトラブルに遭ったことがある九条林檎さんに聞きました。
(※1)他人のイラストをトレース(なぞり描き)し、盗作する行為

目次
- 「リスクは高い」九条林檎がファンアートをサムネイルに使わない理由
- ホロライブの大神ミオが巻き込まれた騒動、どう対応すればよかった?
- 参入ハードルが低い生成AIのメリットと問題
- ファンアートが支えるVTuberの活動と再生数
- 果たしてAIイラストと明記しなければいけないのか?
- AIイラストから感じ取りづらい描き手の感情
──今回のテーマはファンアートと生成AIです。なお、本稿におけるファンアートは、「ファンによる二次創作イラスト」と定義しています。林檎さんはファンアートをサムネイルに使用することはありますか?
九条林檎 我は、ファンアートは使わないことにしている。生成AIでつくられたイラストでも、手描きのイラストでも、問題が発生するリスクはあるからな。どんなイラストも、他者の著作物を侵害していないかどうかは、証明するのが非常に難しい。確定させるならそれこそ法廷の判断になるな。なので基本ファンアートはサムネイルに使わないのが我の方針だ。
──生成AIが一般的に普及する前からそうしているのでしょうか?
九条林檎 そうだな。6年前のデビュー時からずっとこの方針だ。我は色々なイラストレーターの方にイラストを描いていただいてきたが、そのうち1枚がいわゆるトレパクをされ、某大手事務所のVTuberのファンアートとして描かれたことがあった。そして、そのトレパクをされたファンアートが配信のサムネイルに使われてしまったんだ。
我と利害関係者は揉める気はなく、損害が大きいわけでもなかったので削除依頼などは出さなかったが、この一件でやはりファンアートを使うリスクは高いと改めて感じた。
──林檎さんと同じくファンアートを活用しないVTuberもおられますが、リスク回避のためそうしているのでしょうか。
九条林檎 一概にそうとは言えないが、可能性は低くはないだろうな。ほかには管理リソースが捻出できないからだとかブランディング上の事情だとか、単純に自分の顔をしっかりサムネイル上で出していきたいという戦略的な理由もあろう。
──ファンアートを自分のコンテンツに使う方は、チェック体制が万全だからなんでしょうか?
九条林檎 どうだろうな、なにぶん自分とは違う方針の方の話なので我もはっきりとはわからない。しかしチェック体制が万全だからファンアートを使うよりは、やはりファンとのコミュニケーションの一貫であったり、ファンの力を活動に活かす、みたいな動機であり、チェック体制に関してはあくまでもトラブル防止機能の枠を出まい。
我の知っている範囲では、毎回反社チェックなどをして厳密に確認しているような者はいない。
──最近だと、生成AIによるイラストをサムネイルに使用していると指摘された大神ミオさんが当該のイラストを変更。一方でイラストの制作者は生成AIでつくっていないと主張し、騒動に発展しました。
正直な話、指摘された時点で相当困難な状況ではありますが、もし林檎さんが同じお立場だったらどうしていましたか?
九条林檎 まず、ここら辺の事情に明るくない者のために、なぜ生成AIによるイラストだと指摘されたら削除する者がいるのか説明しておこうか。
そもイラストの生成AIをざっくり説明すると、AIが色々なイラストの要素について学習(パラメータへの分解)し、要素のるつぼのようなモデルを形成する。そしてプロンプト(指示)に最も近いと思われる要素をるつぼから取ってきてイラストにするというようなものを指す。
極度に単純化するなら「リンゴの絵を沢山見たところ、赤くて丸い形が多いようだな」と学習し、赤と丸のパラメータを強めにしたイラストを出すとかそういう形だ。
しかし学習元となるイラストに関して、一部のクリーン志向のものを除き、基本学習の許可を取っていないことがほとんどだ。現行の日本の法律では不法行為にならないとかそういうことは一旦置いておいて、快く思わないイラストレーターの方は多く見受けられる。
──心情的な問題ですよね。
九条林檎 生成AIの学習は、人間が色々なイラストレーターの絵を見て練習し、段々と上手くなって自分の描き方を確立するのとは時間も手間も規模も違う。しかも大体企業が商業的な目的のためにモデルをつくるわけだな。
描いているのも個人クリエイターがほとんどで、そういった人々の絵を、大企業から投資を受けている企業が勝手に自社の製品をつくるリソースとして利用する図は、確かに一種搾取的に見えるし、不法行為ではないと言われても心情的に受け入れられない、嫌悪を感じるのはわかる話だ。
だから現状に強く反発する方、権利を侵害されていると感じている方が多いわけだな。特にネット上のイラストは二次創作も多く、それが商業的に利用されることにそもそも反発が生まれやすい。
実際現状の仕組みだとイラストレーターの方々に特に金銭的な利益も発生せず、むしろ仕事の機会が減る分マイナスだ。なにぶん規模が大きいので、影響は「自分より安く描くイラストレーターがいて仕事が減る」という状況の比ではない。
そういうわけでイラストレーターの方々の仕事を保護する意図、または配慮するために生成AIを使っているイラストは使わない、万が一使ってしまって生成AIだとわかったら削除される方がいるんだ。
──VTuberとイラストレーターの関係は切っても切れませんからね。
九条林檎 そうだな。しかし、あるイラストが生成AIでつくられていないとネット上で証明するのは、非常に大変だ。
生成AIでつくられたイラストかどうかを確認するAIチェッカーのようなツールを使っていたとしても、精度はあまり良くなく、やはり証明にはならない。手描きであることを証明するために、作業中の工程をタイムラプスにする方法もあるが、そのタイムラプスをつくる生成AIもあるしな。
先ほども言ったように、たとえ生成AIだとて著作権を侵害しているかの判断は法廷に任せるほかない。「不法行為でないのに責めるべきではない」と主張する人もいるので、大神ミオ氏がどんな対応をしていたとしても、万人を納得させることは難しかっただろう。
大手事務所のVTuberだと影響力も大きいため、対応は非常に考えあぐねるものだったであろうことが察せられるな。
続きを読むにはメンバーシップ登録が必要です
今すぐ10日間無料お試しを始めて記事の続きを読もう
残り 6780文字 / 画像5枚
800本以上のオリジナルコンテンツを読み放題
KAI-YOU Discordコミュニティへの参加
メンバー限定イベントやラジオ配信、先行特典も
※初回登録の方に限り、無料お試し期間中に解約した場合、料金は一切かかりません。
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介

ラッパー/ライター/編集
現代の日本の音楽シーンを語るなら、ボカロ文化は不可欠。2020年代のボカロ曲において、音楽的な独自性はどこにあるのか? 柴那典さんが「MAJ2025」受賞候補曲から考えます。
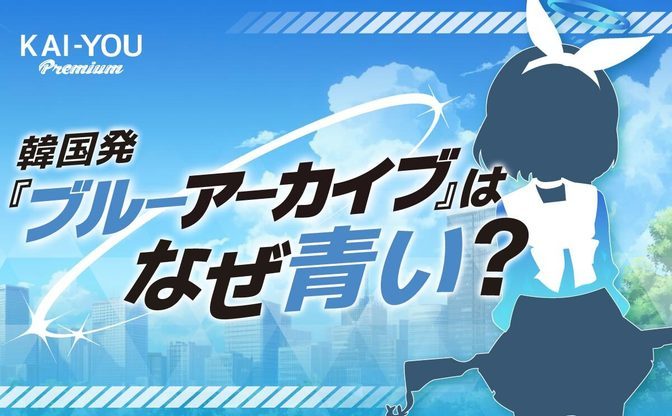
ライター
『ブルーアーカイブ』の青い色彩設計、そしてエデン条約のストーリー。この2つを柱に日本のサブカルチャーがアジアにどんな影響を与えたか、韓国でどう花開いたかを紐解きます

ライター
ぶいすぽっ!所属の蝶屋はなびさん。普段から前向きな姿勢を崩さない彼女のひたむきさはどこから来ているのかうかがいました。格ゲートークも充実!

編集
語られざる、違法な海賊版トレーディングカードゲームの歴史。世界広しと言えども、この解像度でその歴史を紡げる人は、SF作家・ゲームコレクターである赤野工作氏しかいない。

編集
結局、同人誌って違法なの? 実在する「VTuber」の二次創作、もしかして肖像権侵害や侮辱罪に当たっちゃう? 令和版、同人文化への最新の法的動向を弁護士に根掘り葉掘り聞いてます。

編集
日本語ラップを、構造的に理解する──音楽としてでもライフスタイルとしてでもない、新しいヒップホップの解釈を提示してもらっています。

編集
オタク/ラップのトップランナーだからこそ語れる“ニコラップ”の世界。懐かしいだけじゃなく、今に接続される話になっています。

ライター・編集者
減らないVTuberの活動休止について、根本的な原因を九条林檎さんに聞きました。推しのVTuberがいる方は、ぜひ読んでもらいたい内容です。